「うちの猫、腎臓が弱いって言われたんだけど、なんでだろう?」
猫を飼っている方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。猫の腎臓病は、高齢になるにつれて発症する確率が非常に高く、多くの飼い主さんを悩ませる病気です。でも、なぜ猫はこんなにも腎臓病になりやすいのでしょうか?
実は、その理由には、猫たちの「祖先のルーツ」が深く関係しているんです。今回は、獣医さんから聞いた興味深いお話も交えながら、猫が腎臓病になりやすい秘密と、私たち飼い主ができることを徹底解説します!
イエネコの祖先は「砂漠の住人」だった!?腎臓との意外な関係
獣医さんと腎臓の話をすると、必ずと言っていいほど出てくるのが「イエネコはどこからやってきたのか?」という問いかけです。
最新のDNA解析の結果、驚くべき事実が判明しています。なんと、私たちと暮らすイエネコの祖先は、約13万1,000年前に中東の砂漠などに生息していた「リビアヤマネコ」であることが分かっているんです!
この「砂漠の住人」というルーツが、猫の腎臓の弱さにつながっていると考えられています。
- 水分温存のスペシャリスト: 砂漠という水が貴重な環境で生き抜くために、リビアヤマネコは体内の水分を最大限に温存できるよう進化しました。その結果、彼らは少量の、非常に濃縮された尿でやっていけるようになったんです。
- ネフロンへの負担: しかし、この濃縮された尿を生成する過程で、腎臓内のネフロン(腎臓の機能単位)には大きな負担がかかると考えられています。以前のブログでも少し触れましたが、猫科の動物はもともとネフロンの数が人間や犬に比べて少ないんです。ネフロンは一度ダメージを受けると再生しないため、この「濃縮尿」が、長年にわたる腎臓の消耗につながってきたのかもしれません。
つまり、猫の腎臓が弱いのは、彼らの祖先が過酷な砂漠環境を生き抜くために手に入れた「水分温存能力」の、ある種の代償とも言えるのです。
「遺伝」も深く関わる!腎臓病になりやすい猫種とは?
さらに、獣医さんから聞いた驚きの情報があります。特定の猫種では、他の猫種に比べて2倍以上もの確率で腎不全になりやすい傾向があるそうです。それは、「家族性腎症(遺伝性腎臓病)」といって、家系的に腎臓の代謝障害が多い猫たちなんだとか。
具体的には、以下の猫種が腎臓病になりやすい傾向にあると言われています。
- ロシアンブルー
- メインクーン
- アビシニアン
- シャム
- バーミーズ
これは、私が昔飼っていたロシアンブルーが先天的に内臓疾患を抱えていて、その時お世話になっていた獣医さんから教えてもらった話です。私の愛猫ヨシカゲちゃんも、ロシアンブルーの血を引いているせいか、小さい頃から尿路や腎臓でトラブルを抱えることが多かったんです。
もちろん、このリストに載っていない猫種でも腎臓病になる可能性はありますが、これらの猫種を飼っている方は、特に腎臓の健康に注意を払う必要があるでしょう。
腎臓病予防は「日々の食生活」から!飼い主ができること
猫を飼い始めたばかりだと、可愛い猫の餌選びに夢中になって、なかなか腎臓の健康まで意識が回らないかもしれませんよね。でも、先天的な要因は抜きにしても、日々の食生活が腎臓の劣化スピードや健康に大きく影響することは想像できると思います。
- 水分補給の徹底: 腎臓病予防の基本中の基本は、水分補給です。猫はあまり水を飲まない傾向があるので、常に新鮮な水を複数箇所に置いたり、ウェットフードを積極的に取り入れたり、循環式の給水器を試したりして、飲水量を増やしてあげましょう。
- 高品質な食事選び: 腎臓に負担をかけない、良質なタンパク質を含んだキャットフードを選ぶことが重要です。安価なフードには、腎臓に負担をかける可能性のある添加物や質の低いタンパク質が含まれていることもあります。
- 適切な栄養バランス: 特に、リンの過剰摂取は腎臓に負担をかけると言われています。腎臓病の初期段階であれば、リンの含有量が調整されたフードを選ぶことも検討しましょう。
- 定期的な健康チェック: 猫は病気を隠すのが得意な動物です。日頃から飲水量や尿の量、食欲、体重の変化などをよく観察し、定期的に動物病院で健康診断を受けましょう。特に中高齢の猫ちゃんは、年に1〜2回の血液検査や尿検査で腎臓の機能をチェックしてもらうことが非常に大切です。
まとめ:愛猫の腎臓を守るために、知ること・行動すること!
猫が腎臓病になりやすいのは、彼らの遠い祖先が砂漠で生き抜いてきた「進化の歴史」が関係していると考えると、なんだかロマンを感じますよね。そして、特定の猫種が遺伝的に腎臓病になりやすいという事実も、私たち飼い主が愛猫の健康を守る上で知っておくべき重要な情報です。
今日の話が、みなさんの愛猫の腎臓の健康を考えるきっかけになれば嬉しいです。日々の食生活や生活習慣を見直し、もし心配なことがあれば、迷わず獣医さんに相談してくださいね。
愛する猫との幸せな毎日を、一日でも長く続けるために、私たち飼い主ができることを一緒に頑張っていきましょう!
ニャゴニャゴ!
人気ブログランキング





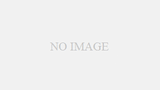

コメント